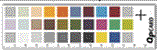| ||
| | ||
| コンテンツ | ||
| はじめに | ||
| トーンリプロダクション | ||
| O/G変換 | ||
| icc profile のグラビア的利用 | ||
| プロ用製版スキャナー | ||
| 仕事に役立つ 視覚の法則 | ||
| 版の精度とは何か? | ||
| グラビア版の値段 | ||
| グラビア製版エキスパート試験 | ||
| 今後まとめようと思う項目 | ||
| 更新履歴 サイト作成 | ||
| DTPエキスパート認証試験 独学受験必勝法 | ||
| my personal affair | ||
DTPに役に立つリンク集↓ | ||

あなたは「オフセットインキと同じ発色のグラビアインキがあったらいいのに」と思ったことはないですか?
グラビア製版をやっているのに、デザイナーがつくる色見本はオフセット印刷に準じた出力物です
「井上さん、お客さんは写真の色は色見本通りということですから、色目はこれにピッタリ合わせてといてくだいね」
井上(私):
「グラビアインキで刷るんだから、同じ色になるわけないだろが・・・グラビア製版の営業なんだから、お客さんにオフセットと比べると、もうちょっとボリュームがでますとか、鮮やかになるとか、ちょっと色が変化するニュアンスをお客さんに伝えてこっちの逃げ道つくっといてくれよ!(バカたれ!:心の声)」
とは、現役時代に営業とよく交わした会話です。
案の定、製版が完了して、最後に校正刷し見本と見比べると、ハンバーグの照かりが紫色してたりして、どう見ても色見本と同じに見えない。困ったなー。「赤インキ薄めて、もう一度校正しようか?坂本さん」、が、それでも、まだ赤い。「どうしようかな。お客さんの許容範囲は結構広いんじゃないか!?もう時間もないし、これで出してみるか?」ヨッシャ!
しかし、もし、本機の立ち会いでダメがでたら、どうなるか?
休日出勤でやり直しをして乗り切る悪夢が待っている。トホホ
本題に移ります
ちょっと前置きが長かったですが、こんなときオフセットインキと同じ発色のグラビアインキがあったらといいと思いませんか?
グラビア用の色分解に携わった人なら一度はそう思ったことがあると思います。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
仮にオフセットでうまく印刷できたデータがあるとして、
オフセットインキ発色のグラビアインキで印刷したら、たぶん、全体に藍浮きした刷り物になるでしょう。
それはなぜか?
オフセット感覚ではデータの%が、そのまま、刷版に移され、同等の%になるという当たり前の暗黙的了解がありますが、グラビアにはそれがありません。
簡単に図解すればこうです。
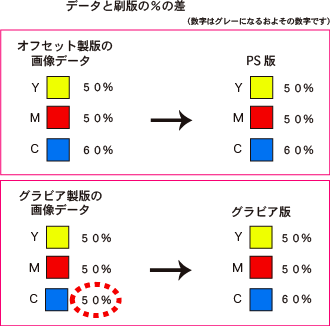
なぜグラビアは50%の網点をわざわざ60%にするのか?オフセット製版だけやっている人には疑問がわいてくると思います。しかし、実際にグラビア製版ではこのようにやっているところが多いんです。
オフセット的に考えるなら刷版の焼き度を変化させてツジツマをあわせているのと同じです。
なんでそんなことするんですか?井上さん
という声が聞こえそうですが、それを解説するにはグラビア製版の歴史から説明しないといけなくなるんです。
要するに、これはグラビアの忌まわしき慣習なのです。
簡単に言えば、昔はグラビアはウサギで亀のオフセットより早く走れるので、ちょっとサボって寝ている間に亀に標準化というゴールを奪われてしまったということです。
より詳しく解説しますと、グラビアはオフセットのようにフィルムをPS版に重ね合わせて1対1の瓜二つの版をつくるという歴史がありません。
データ(フィルム)と刷版は全く別物なのです。
グラビア製版ではまずオフセット的な校正刷り(DDCP)を出し、校了となってから本番の版を作ります。オフセットの網点を何らかの方法でグラビアの網点に変化させる作業を試行錯誤でやってきた変換方式の進化がグラビア製版の歴史とも言えます。
要するに原因はヘリオの発明が早すぎたことにある?
グラビアではオフセットの網点をスキャンして、一旦電気信号(データ)に変えてグラビアの網点に変えるとういうCTP的な自由度の高い調子変換を30年以上前からヘリオクリショグラフという機械(時価一億円!)で行ってきました。ヘリオが1990年代に発明されれば、オフセットとDTPとの相乗効果でグラビアの標準化が可能だったかもしれません。そうです、あまりに発明が早すぎたのです。
そのため、悲しいかな、グラビア製版は各社各様のやりかたで進んでいってしまいました。
私はここで強く言いたいのは、初心に帰れということです。
へリオが発明された当初は、オフセットで印刷できたフィルムをそのままヘリオにかければ、オフセットと同等のものがグラビア印刷として仕上がるというのがヘリオのO/G変換の基本でした。(O/G変換=Offset/Gravure変換)
しかし、実際は、それが標準として徹底されず。現在、各印刷会社や製版会社ごとにO/G変換カーブは違っています。ということは、各会社でヘリオ用に作るデータがそれぞれ違っていてグレーのYMCのバランス%が各社違うということです。そのオフセットとグラビアの調子管理の違いの溝を埋めるべくICCプロファイルなどでの色合わせが盛んに行われて言いますが、私は本末転倒と考えています。製版作業の神髄は網点を読む能力の質にあります。
話を元にもどします。ですので、せっかくオフセットでうまく印刷できたという血統書付きのデータでも、グラビアでは、自分の会社用のヘリオのカーブに合わせなくてはいけないので、そのデータをいちいち自社用に変換しなければなりません。写真部分に関する作業としては、作業の大半がこの仕事(YMCKからYMCKへの変換)になっていて色修正とかの色調の独自性や差別化は二の次になってしまっています。
こう考えてみると「自社用に変換」は実に忌まわしき慣習と言うべきでしょう。
しかし、グラビアの現場では「自社用に変換」が当たり前で、無駄な作業をしていることに気がついていないところが多いです。
へリオ導入時、こうしとけば良かった
オフセットのjapan colorで印刷したものを基本にして、自社のDDCPをjapan colorで調整し、オフセット(画像処理)のデータの網%は変えないというやり方を現場に周知徹底してから、ヘリオの調整をしておけばよかったのです。設備導入の最初にです。
そうすれば、デザイナーには「うちのグラビア用のデータはjapan colorにのっとってデータを作ってくれればいいですから」とだけ言っておけば済むのです。デザイナーが自社のヘリオの変換までしてくれるのと同じ効果になります。
この手法は管理職的に考えれば、大きな合理化です。また、オフセットとの親和度が増し、逆にグラビアのデータをオフセット化して紙に印刷するのも楽です、また、オフセットの網%に慣れた作業者がグラビア製版に移行しやすくなり印刷方式のborderless化も促進され、とりもなおさずグラビアの孤立化を防ぐ普遍性をもったやり方でもあります。
製版現場では、私が推奨するこのやり方に賛成してくださる方も時々いらっしゃいます。しかし「今更直せないですよ」という共通の返事が帰ってきます。
そんなことしても結果は同じだから現状のままで良い、というのが直そうとしない理由です。しかし、このやりかたは品質にも影響してくるだろうことが最近自分なりにわかってきました。コントラストのないものを刷版で無理矢理コントラストをつけようとしたらどうなるか?
要はさらに良いものを求めるか否かです。もっと真剣に考えても良いテーマかもしれません。その辺は、違うページでとりあげるつもりです。
2006.9.18