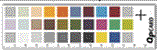| ||
| | ||
| コンテンツ | ||
| はじめに | ||
| トーンリプロダクション | ||
| O/G変換 | ||
| icc profile のグラビア的利用 | ||
| プロ用製版スキャナー | ||
| 仕事に役立つ 視覚の法則 | ||
| 版の精度とは何か? | ||
| グラビア版の値段 | ||
| グラビア製版エキスパート試験 | ||
| 今後まとめようと思う項目 | ||
| 更新履歴 サイト作成 | ||
| DTPエキスパート認証試験 独学受験必勝法 | ||
| my personal affair | ||
DTPに役に立つリンク集↓ | ||
トーンリプロに戻る>
等価中性濃度について
「トーンリプロダアクション」と同様で「等価中性濃度」という言葉は、まるで死語になった感があります。
しかし、このふたつの言葉をどのくらい体系化しては把握できているかで製版オペレーターの調子の再現力に差がでます。
icc plofileを鵜呑みにせず、製版やってるなら是非これらの概念を、このサイトで持ち帰ってください。
話は少しそれますが、製版の現場では、「よその会社の製品より優れたものをつくる」ことより「よそとそっくり同じものをつくる」という仕事のほうが数段難しいのはご存知かと思います。
その作業の頻度は、包装用のグラビア製版では結構多いですし、営業的にも大手メーカーからの最初の注文がとれるかどうかの瀬戸際の時にこういう作業が要求されます。それに技術的な面では、今のところ、その作業を自動化する装置はないので、唯一残された職人芸です。ということは、会社の技術力が問われる場面であるということです(体外的には会社ですが、社内的にはスキャナーオペレーターの能力で決まります)
話がさらに逸れますが「よそとそっくり同じものをつくる」という作業の裏技をここで公表します。もらった見本(印刷物や原稿)そのものを一度色分解してみるんです。その分版と見くらべながら、それに合わせていくのが意外と近道なんです。
ノウハウの詳細は後日別ページに書くつもりです。(ヒントは、どのくらいピントをずらしてスキャンするか?のモアレ対策です。photoshopなら一回ボカしてからシャープネスをかけるという「見せかけのシャープネス」の手法ですね)
「えっ?それなら最初から見本の印刷物を直接スキャナーにかけたものを使えばいいじゃないか?って」、これは著作権上問題になるのでだめです。それにモアレが出て、とても現場で使えるほどの品質になりません。やってみれば一目瞭然です。
本題にもどって
「そっくり同じものをつくる」ためにはスキャナー操作の基本を学んでいるかどうかが、経験と同じくらい重要です。
たとえば、スキャナーでライトの赤版のセットアップを明るくしたい時の変更方法として、3%とでている数字ををマイナス5%とかにする方法(ポジ出し)とキャリブレーションの100の数値を108とかにしてレンジを変える方法の2種類があります。この差は階調にどういう差がでるか?わかりますか?
私は大日本スクリーンのスキャナー研修ではキャリブレーションはいじってはいけないと教わりました。しかし、DC350のドイツ的インターフェイスのスキャナーはキャリブレーションのツマミを使わないとセットアップができないように作られています。スキャナーの設計者の調子再現に対する考え方がインターフェイスにの違いにもでているのです。どちらが正統派か?は私にはわかりませんが、キャリブレーションをいじると中間調も変化してしまいますが、薄いグレーの再現に劇的効果があるのを確認しました。キャリブレーションのツマミを手動で回すことが邪道とは言い切れないと思います。それなりの実践的効果があるからです。
ちなみにphotoshopの階調表現しか知らない人には、今の話はわからないと思います。そういう機能が、photoshopには付いていません。カーブの調整の欄に105%もマイナス5%という数字もないし、そもそもデータというものに濃度レンジの概念がないです、カーブの縦軸と横軸両方とも%になっています。
これでは写真にはあった階調がこの段階で全部0%や100%に収束してしまっています。
最近、RAWデータを扱うようになったんですが、 RAWデータなら、ある程度「まな板の上の鯉」状態が再現するのでスキャナーオペレーターの腕が発揮できます。 「まな板の上の金魚」ではすでに手の施しようが無いです。
つまり、極ライト極シャドーの階調を「ゴミ箱」から拾えるようにしておかないと製版現場ではどうにもならないということです。 RAWデータ入稿はダメとよく本に書いてありますが、それはナンセンスだと思います。どう加工したかのsetupのプロファイルさえあれば、RAWデータ入稿の方が最高のものがあがります。
カメラマンが印刷の仕上がりまで把握して、完璧に色調整するより、カメラマンがベテランのスキャナーオペレーターと直接会って、自分の意向を思う存分伝えたほうが、良い物ができるというのが、私の持論です。なんといってもスキャナーオペレーターは期待色をつくるプロなんですからね。
完璧な状態で入稿したい気持ちはわかります、時代もそういう流れです。でもそれは自己満足にすぎません、最期には妥協して写真集をだしたカメラマンの話はよく聞く例です。
(注1「直接会う」のは現実的には難しいです。あくまでも私の理想論です)
(注2「記憶色」は色彩用語ですが「期待色」は色彩用語ではありません、お客さんの期待する色と言う意味です。写真や印刷の営業用語ではないでしょうか?)
ここのページは書きかけです。
トーンリプロに戻る>
2006.9.18 初回作成
2007.9.23 文書追加